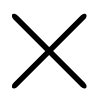日記
晴れと褻
晴れと褻(け)
といって、今どれ程の人に通じるのでしょう、
私の代でも普通にこの言葉が出る人は少なく。
船場育ちの大姑が、この頃は毎日ご馳走で毎日お祭りや。そう面白く無さそうに言っていたのを思い出して。
子供の頃はお正月に新しい下着と歯ブラシが用意されていて、日本髪を結いお正月の晴れ着を来て初詣につれていってもらいました。
行事ごとはいつもちゃんとしてくれて。
法要やお祭りはそれはお人がよって賑やかなものでした
そんな営みはその時代の当たり前だったのかも知れません。いやもっと日本の世界のはたまた人類の自然の営みであったのかもしれません
自然のなかで生きてきて、災難災いと共にあり、そのなかで生き延びていくことの恐れと感謝が様々な年中行事となり祝祭となり。そのなかで精神的なけじめができ安定となっていたような。
今は何事も苦労なく贅沢となり…,
大姑のため息も納得させられるものが。
自然の恐れが少なくなったとはいえ、越えられぬ驚異はまだまだこの世にあり。疫病も病も死も普遍に身近にあり、はたまた重労働の農作業はなくなったとはいえ、機械化が進んだ世の中で心身の重労働は加速して。
時代にも晴れと褻があって。お化粧もせずに子供を乗せて自転車で走り回り、パジャマに着替える力もなく子供と共に寝落ちしたことも多々。立って台所で食事をしたり…。
子育て終われば親の介護でまた寝るまもなく、
そんな日々を経て、少しできた時間で日本の世界の文化を楽しむこともでき。ようやく晴れも味わえる様に
様々な晴れと褻。
晴れを知らなければ本当の褻もわからず、褻も知らなければ本当の晴れもわからず
若いお母様がたに書と共に年中行事や季節の言葉もご教授させていただきながら、お人としてまた親として晴れと褻を意識していただくひとときがあればと、ことさらに思う。
日常を大切に丁寧に過ごして、そして様々と学び教わってきた晴れの時をしっかりと味わい過ごして、日本の営みをリズム?を日本人として大切にしていきたいと、そう思うのてす