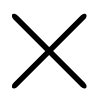日記
教養講座
朝から、ロイヤルホテルロイヤルルームにて満席の中教養講座を拝聴。なんと活気のあること
成田山書道美術館学芸員。大東文化大学教授の高橋俊郎先生のお話。
戦後の書をその時代を牽引された偉大な書家の方々の書への考え、行動、そして作品を見せて頂きながらその当時の書檀に思いを馳せる
伝統と未来へ向けての脱皮。
その苦悩の道のりを省みさせてもらい。
書が芸術に至った道のり、であること、またその真髄であるところの精神性、様々な葛藤の歩みはその書にしっかり現れて。
まさに書は人なり。全てが写し出される。
戦後の書を牽引されてきた書家の中に歐亭先生は当然のように名を連なれ、その新たな書は脈々と力を付けて。
現代の書家として石飛先生の名があがり、現代書道二十人展において石飛先生の名が挙がったことは、創設70年かかって、近代詩文書が伝統となり得たことを示していると。
毎日書道会にとってはアウェイ?でもある袂を分かった人々の中からもなっとくの様子が垣間見られ、師のそのまた師の懸命に歩まれた新しい書の確立の道のりとその今を感じて心が熱くなる
書聖王羲之も道教に真髄し。書は日本の仏教においてもなくてはならない修行となりえて。
また貴人としての何よりの教養でもあり得た書。
書の学びというものは人の学びに成長に不可欠なものであり。本当にそうだと思う
先人の書を語る思い、その自らを絞り出すかのように書かれたその人そのものの書を見るに、とてつもないものであることだけはひしひしと伝わり。
高橋先生の解説のお陰で、さらに深く想いを馳せ見えなかったものも見させてもらい。これからの書に向き合い、表現していく上でとても素晴らしい気付きを与えていただけました
そして何よりもなんとなんと情けない自分を思い知らされる
この日に感謝