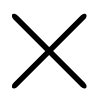日記
笑み
ある再会のおり、両親がとてもとても喜んでくれました。
二人揃って来てくれて、満面の笑みで。
大丈夫。
大丈夫だよ。
大切な大切なご縁です。
夢
母が来てくれました
吉夢と。
心配かけてごめんね
会話
パドマ保護者クラスでの会話。
ある方の思いが心に染み渡り、少しお話。
今まで教えていただいたこと、思いが溢れたこと、経験したこと、色んな気持ちがまざりあって、素直に言葉が発せられました。
前の法要のご法話で、現園長先生(ご老僧)が前園長先生から、自然に口から南無阿弥陀仏とでるようになったら一人前やと。おっしゃったと。
そんな境地には到底至りませんが、人との会話でもそうありたいと、とても思えた瞬間
仏教教育
パドマ幼稚園70周年記念祝賀会が行われました
仏教学者釈徹宗先生の講演もあり、仏教幼児教育の大切さを語られる
初代園長先生が志半ばでこの世を去られ、二代目園長先生はその思いを懸命に受け継がれ、その生涯の全てを仏教と幼児教育に捧げられ、パドマの仏教教育の礎をつくられました。四役として園活動にご奉仕させていただき、様々な方々にお助けいただきながら、身も心も修行のように成長させていただきました。
現園長先生も個性豊かに引き継がれ、今の時代になっても普遍に存在する一つの教えとなりました。
現園長先生のお話をある方としていたとき、ほう、なかなか面白い人物やなと嬉しそうにおっしゃってくださいました。今その事が身に染み、今あることがありがたく感謝の気持ちで一杯です。
子供たち、若いご両親、先生方、懸命に勤められる方々に囲まれて、すばらしい教えを頂いています。
100才中野北溟先生の、まだまだ、怠けたらいかんと言う言葉が胸に響く。日々学びと。心に
母心
お母さんはいやというほどやってきたから、そのさきが見てみたいのです。そのさきに行ってみたいのです。