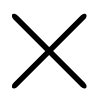日記
夢
ありがたい夢
法要のお陰
ありがたいこと
これからの道に
大切な宝物
道
ある時、心落ち着く大切な場所で、のらりくらりとしていたら、まっすぐに果てなく延びる道が心にうつり、ある時は龍のように果てなく伸びゆく金の光が心の中に見えました
昨日生駒に行くときには素晴らしい空に重なり天に向かって伸びゆく綺麗な二本並んだ雲があって
今までも、そしてこれからも道を進んでいくための大切な大切な心の宝物
これからも見えた道をまっすぐに参ります
心
心の中に小さな灯がともり。
小さな願い、そして果てしなく大きな願いが、そして夢のような願いが見えました
心に灯ったものは、身体を抜け出し叶ってくれるのでしょうか?
今見えぬものが、悲しいことでないようにと
心から願う
現実とは…現実とは?
現実とは…
関ヶ原
晴天
沢山の雪が積もって
懐かしい景色
雪が輝いて
空を見ればなんと雄大な雲が
調べものをしていたら、何だかどなたかのブログが出てきて、ご縁のある人とは再び出逢えると。そしてお世話になったドクターのお名前が語られていて。
不思議なこととはあるもので
そう思えばそう思え
思わなければ何の不思議もないのだけれど
見えない糸は皆つながっていて
どんな糸なのでしょう
良い糸でありますように
過去帳
何年かぶりに息子の中高の時のママ友から連絡あって、過去帳書いてほしいとこられ。
お仏壇を新しくされたときに、書かせてもらったので。またわざわざ来られて新仏さんができられたのだなぁと。
忙しいのにごめんね、と。
息子にも私たちが死んだら斎藤さんに過去帳書いてもらって、相続のことやら斎藤さんとこのお兄ちゃんに相談しいって言ってあるねんと、にこやかに。
ご自身も会計事務所にお勤めなのでご縁もあるだろうに、斎藤さんとこのお兄ちゃんやったら安心して任せられるので、と。逢ってもない我が息子にありがたいお言葉。
過去帳開けば、新仏さんはご主人とのこと。61歳で。余命一年と言われすい臓がんで。あまりの驚きに思わず手を合わせ、言葉もなくそれしかできず。
落ち着いてひとしきりお話しを聞き、その短くも濃い一年のこと、またその寿命がわかっていたかのような晩年のお導きのような暮らしぶり。
短い人生やったけど、存分に思い残すことなく過ごされたんちがう?と二人で納得もし。
家族葬でありながら、様々とご心配される方々に囲まれて十分に心をケアされる環境にあられたことにも安堵が。
しっかりと見送られて、もうじき七七日とか。
1月に若いお別れが続き。本当に私もそして私の大切な人たちもいつなんどきと、深く思い知らされる。
話を聴きながら、様々なことに思いも巡り。
その時への準備も何もできていないこと。最期の時を思い残すことなく生ききれるかと、今あることこの先に思いを寄せ。とてもとても大切な1日なのだと深くそう思う
まだまだ巡り来るものは沢山にあって、おまけに過去のご縁が様々とまた沢山につながって。まだまだまだまだ現役以上の働きぶりで、まだまだまだまだ精進して勤めなければと思っているけれど
これも最期の時に向かってのお導きを頂いてるのかもしれない