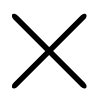日記
線
10年前の作品を再度書き直し
構成も変えて
10年前に先生に封印された線がここに
その線を今見てみると、なんと愚かな浅はかな。
それに酔いしれて未熟とわからず書き続けていたら、今の私はなかった。封印され、すっかりその線を捨てて様々な学びから得た新たな線。
そして生まれ変わって。その兆しも見え。さぁこれから自在に自分の線にと操れるでしょうか。
ひとつ越えた自分を、そしてまた一歩一歩
偉大な師に感謝
夢
毛氈の上でうたた寝
すごい夢を見ました
恐る恐る調べたら
素晴らしい吉夢
これから新たな計画、新たなおもい、新たな道
転機と思うことが山積みのなか、なんとありがたい
そうこの間綺麗な綺麗な心を体験したあと、神戸で教えてもらったことも同じことを
ありがとう
守ってくださいね
がんばります
導き
6歳年上のある人は
旧来の治療で今も病から抜けられず
薬嫌いの私は
その意志を大切にしてもらえて
お陰さまで
今がある
美容室でなにげに開いたページ
迷える苦しむその瞬間にこれだと。今もそのときのことは鮮明に思い出され
本当に導かれたこのご縁は何よりもありがたく
ご恩を忘れたらあかんよ
と言い続けてくれた母の言葉が思い出され
再会の日に来てくれた両親の笑み
本当に喜んでくれてたんやね
ご恩返しはできてますか?
二度見捨てたくないとその時に思った心
そんな傲慢な私でもなにかのお役にたっていればありがたいこと
妄想のなかのお話
でも現実よりも何よりも私にとって何より大切なお話
命のページに
お導きに
今あることに
心から感謝
笑い合い
一番変わったのは
変われといってくれていた人かもしれません
とっさ
ある時の覚書
とっさにでた言葉
行い
その事で
本当の己のなかの深い深い思いを知るのかと
無意識の身体は
何がどれ程大切なのか
愛しいのか
本当の心
真の心を
教えてくれました
それが私なんですね